電話: 090-9884-1961
FAX : 050-3588-4311
MAIL:master@munedong.com
〈読書エッセー〉晴講雨読・許南麒の詩と初版本(中)
《朝鮮新報》2022.04.10
許南麒の2冊目の詩集は『朝鮮冬物語』以降の時事的な詩を集めた『日本時事詩集』である。実は少し前に東京神田の古書店で購入したのだが、その目的は本稿を書くためといってもよい。具体的には民族教育に携わる人が語り継ぐ「これが俺達の学校だ」の初出を知るためである。
「子供達よ/これが俺達の学校だ。/校舎はたとえ見すぼらしく/教室はたった一つしかなく」と始まるこの詩は、元朝連小学校長の詩Ⅱで、「一九四八年四月一五日、東京京橋公会堂で開かれた朝鮮人教育不法弾圧反対学父兄大会によせた朗読のための詩」となっている。
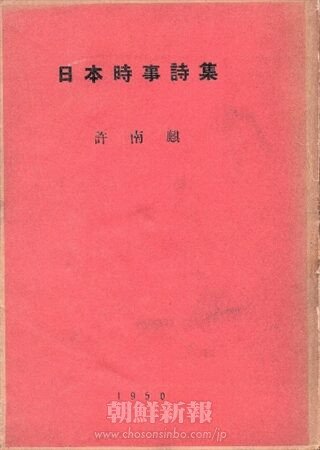
『日本時事詩集』(1950)
同成社版には、Ⅰ「風の中を」、Ⅴ「一九四九年十一月二日」も収録されているが、Ⅰは「一九四七年川口朝連小学校入学式の日」に、Ⅴは「この日川口朝連小学校は閉鎖され子供達は再び日本の学校に送られた」とある。
では同成社版にも全集版にも収録されていないⅢ、Ⅳはどのような詩なのか。時期的にこれらが収録されているのは『日本時事詩集』であり、それも確かめずにはおられなかった。こんなところは、つくづく自分は理系だと思う。
詩集には元校長先生の詩が5篇ともあった。Ⅲは「ポプラのように」、Ⅳは「この先生は」で、Ⅱと同じ朗読のための詩とある。
入学式の日、風の中を歩いてくる新入生を迎え、貧しくともこの学校が異郷で育った子供たちを祖国の空に帰す学校であると校長先生は語る。そして、「朝鮮の山河をうずめるポプラのように/子供達よ/君達元気で育て」と子供たちを見守り、ドーデ「最後の授業」を教えた時に、もし俺たちの学校にそのようなことが起きたらどうしようと涙をぬぐう子供たちを前にして、無力であっても立ち向かうと心に誓う。しかし、その日、学校は閉鎖され日本学校へと転入される子供たちに別れをつげる。
「敵のとりこなって行く朝鮮の同志達、/この先生は/君達を/日本の学校の門前まで送ることが出来ず、/この閉ざされた学校/この傷だらけの校門に立ったまま/君達をおくるのだ。/さようなら、/さようなら、/元気で闘ってくれ、/さようなら、/さようなら、/俺の小さな同志達。」
5篇の詩を通読する時、草創期の民族教育とともにあった学父母と子供たち、そして教員の心の叫びが聞こえてくる。教育援助費・奨学金をはじめとする祖国の温かい配慮と在日同胞たちの熱い思いによって民族教育は輝かしい発展を遂げた。しかし、現在も日本政府の差別政策は変わっておらず、闘いの日々は続いている。
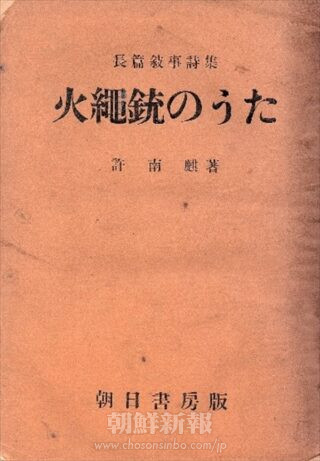
『火縄銃のうた』(1951)
詩集の「あとがき」で許南麒は次のように書いている。「わたくしはいまここに収められている三十一篇の詩をうたう間に、もっとうたわねばならぬもの、もっとうたうべきであった多くのものをうたい逃し見逃して来ました。いや正確にはうたい逃し、見逃してしまったと言うべきかも知れません。どちらにしても闘いと憎しみこそをうたわねばならぬ詩人のひとりとして自分の勇気の足りなさに対する大きな恥じらいを禁ずることが出来ません。」
この詩集が朝日書房から発行されたのは1950年11月で朝鮮戦争が起こってすぐである。そこに至る殺伐とした雰囲気のなか、詩人は「闘いと憎しみをうたう」ことを自己の使命としたのである。
さて、詩人・許南麒の名声を不動のものとしたのが長編叙事詩『火縄銃のうた』であることに異論はないだろう。これが3冊目の詩集である。
「ジュㇴア/お前は いま銃を磨いている/お前は いま/聞慶島嶺の樫の木と/忠州山間の銑鉄でもって出来た/そのかみの 百両の銃/この祖母が/嫁入り道具に持って来た/衣装一切と/銀の指輪と 銀のかんざし たたき売って/ようやく祖父さんにもたすことの出来た/その 火縄銃を磨いている。」
その火縄銃を持って、祖父は東学の乱を闘い、父は三・一人民蜂起に参加した。そして、息子は今朝鮮戦争に向かおうとしている。祖母はその孫の姿を見守りながら朝鮮民衆の物語を語る。「ジュㇴアお前はいま銃を磨いている」というフレーズは何度となく登場するが、それが一種のリズムとなり長編にもかかわらず読者を惹きこむ。
プロレタリア詩人・小熊秀雄は長編叙事詩『飛ぶ橇』の序で、日本には俳句短歌などの根強い短詩形の伝統があり、それを打ち破る長編叙事詩の創作は質的に量的に充実させることは難しいとしながらも、「僕はいま日本に叙事詩が生まれなければならない現実的な環境と必然性とを考え当分この長詩の形式を追求していきたい」と書いた。そして、それを実践するのだが、実は彼以前に優れた長編叙事詩を発表した人物がいる。槇村浩で、彼が残した「間島パルチザンの歌」こそ、日本における長編叙事詩の嚆矢といわれている。
全集版解説では、『火縄銃のうた』の登場は衝撃的な「事件」であったとし、槇村浩、小熊秀雄、そして許南麒に続く長編叙事詩の系譜を確認している。三人にこのような接点があるとは思いもしなかったが、それはけっして偶然ではなく、自分たちがうたうもの、うたうべきものは、長編の叙事詩でなければ伝えらなれなかったのだろう(槇村浩、小熊秀雄については別稿で取り上げる)。
『火縄銃のうた』が朝日書房から出版されたのは1951年7月で、「まえがき」も「あとがき」もなく、装丁もごく素朴である。それだけに、緊要に出版されたものではないかと思われる。翌年に青木文庫の一冊として刊行されたが、ここには「あとがき」があり、この詩を通じて三つのことを訴えたかったと書いている。
まず日本では歪曲され報道されている朝鮮戦争の本質、次に三世代の朝鮮の若者が青春をささげ、女性たちがそれを見守る過酷な運命を担ったこと、そして置かれた状況への日本人への警告である。文庫本は版を重ねたが、それは作者の訴えが多くの人に届いたということなのだろう。
ちなみに、最初の三冊はみな朝日書房から出版されている。何らかの志をもった出版社と思われるが、今はないようである。
(朝大理工学部講師)










